NOTES

UP
芳垣安洋が語るトニー・アレン Part.2 トニーの足跡を辿る14選
Tony Allen『N.E.P.A.』(1985年発表)

ヨーロッパに活動拠点を移してからの最初の作品。分厚いリフとコーラスを前面に押し出した曲があり、世界的に有名になった、同じナイジェリアのフジやジュジュなどの音楽の要素も感じる。構成などもタイトになった感があるが、アフリカ70的なサウンドは残っている。比べると、編成的にはアフリカ70時代よりも少ない人数のバンドでの演奏なのだが、曲によっては、ミックスの段階でエフェクトやダビングなども行われる。
Tony Allen『Black Voices』(1999年発表)

ここ20年のトニーの活動の方向を決めたと言ってもいいアルバム。基本インストで、ドラムのみでアフロ・ビートを進化させ、シンプルな少人数のバンドでジャズやロックなどと新しいミクスチュアを作っていこうというトニーの意気込みが溢れています。クラブ・シーンの興隆と共にトニーの名が世界中に広がりました。演奏にも力が入って、結構音数が多いものもあったり、ビートが一層際立ってきた感じがします。この時期のライヴを集めた『Live』(04年発表)も推薦盤です。
Tony Allen『Tribute to Art Blakey & The Jazz Messengers』(2017年発表)
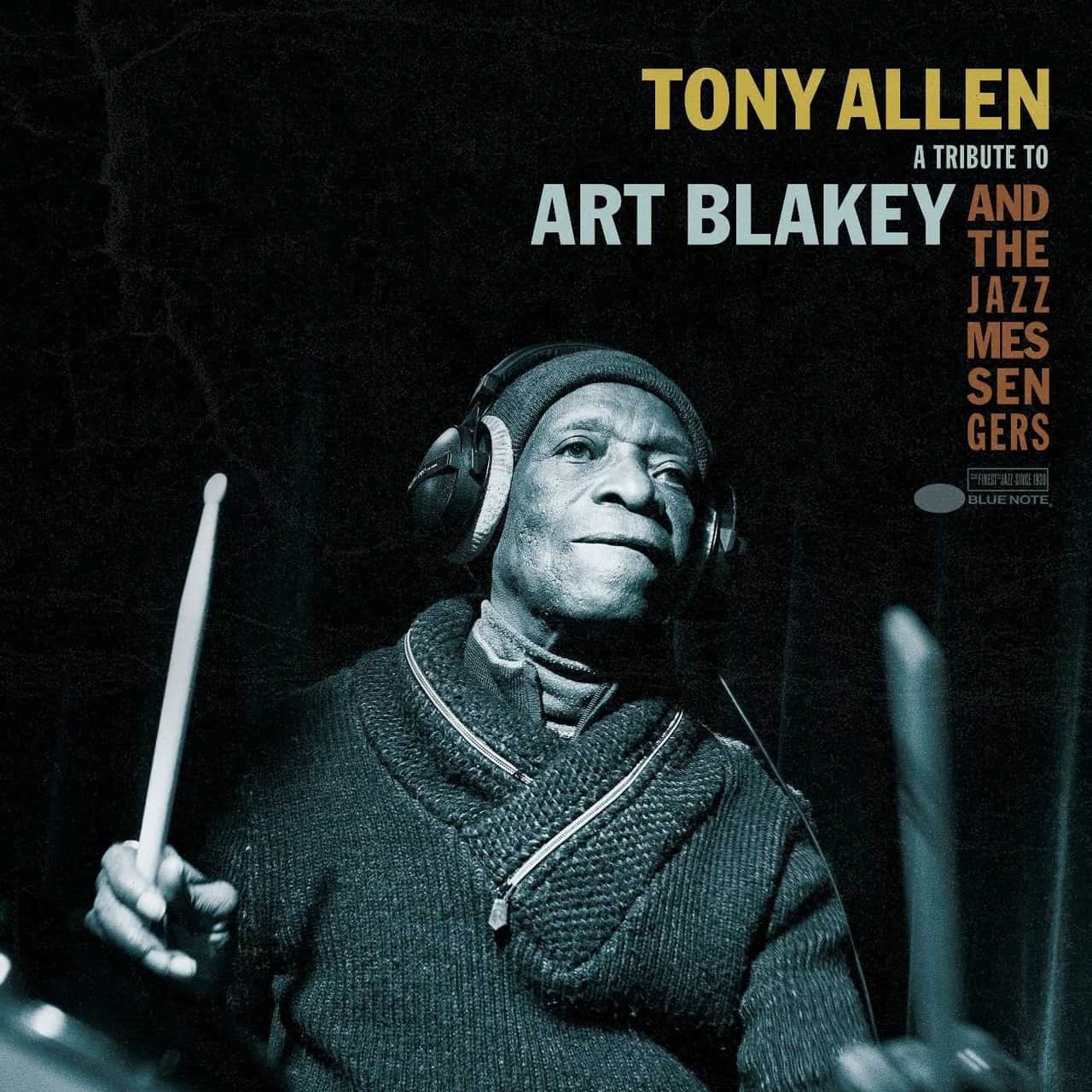
トニーは2017年、アメリカのブルーノート・レーベルと契約してジャズ・アルバムを制作することになり、2作品をリリースしています。第1作目となるこのアルバムはトニーのアイドルだったアート・ブレイキーへのオマージュ。近年活動を共にしていたフランス在住のミュージシャン達との録音で、「モーニン」のアレンジがイカしてます。最後の来日公演はこのアルバムの中からの選曲が中心でしたね。
Tony Allen『The Source』(2017年発表)

ブルーノート・レーベル発での2作品目。ブラス・バンドとの共演で、ニューオーリンズ的な要素も持った独特のジャズ作品になっている。1作目と同じくトニーが活動を共にしてきたフランス在住のミュージシャン達が中心で、サックスのヤン・ヤンキルヴィツ、ベースのマティアス・アラマネはブルーノートでのトニーの作品にはどちらにも参加していて、素晴らしいチームを作っている。もちろんトニーはアフロ・ビートなのだが、これが実にスウィングするのです。
Rocket Juice & The Moon『Rocket Juice & The Moon』(2012年発表)

2000年前後から自分のバンド以外にさまざまなジャンルのミュージシャン達とのコラボが盛んになり、ジャマイカの伝説的ギタリスト、アーネット・ラングリンとも共演しています。UKポップ・スター、デーモン・アルバーンからのラヴコールで作ったThe Good, the Bad and the Queenはおとなしめの歌モノでちょいと物足りなかったですが、レッチリのフリーが参加したこちらのバンドは、噛み合わせが素晴らしく、アフロ・ビート以外の面も見ることができる素敵な作品です。
Angelique Kidjo『CELIA』(2019年発表)

アンジェリーク・キジョー(vo)が敬愛するキューバのシンガー、セリア・クルスに捧げて作られた作品。トニー以外にも、ミシェル・ンデゲオチェロ(b)、ガンべ・ブラスバンド(horn)、シャバカ・ハッチングス(t.sax)など、アフリカ、フランス、イギリスの人気ミュージシャン達による共作。アフロ・ビートがルンバにハマるというのに驚きましたが、トニーのドラムからはクラーベが聴こえてくる。
Tony Allen & Hugh Masekela『REJOICE』(2020年発表)
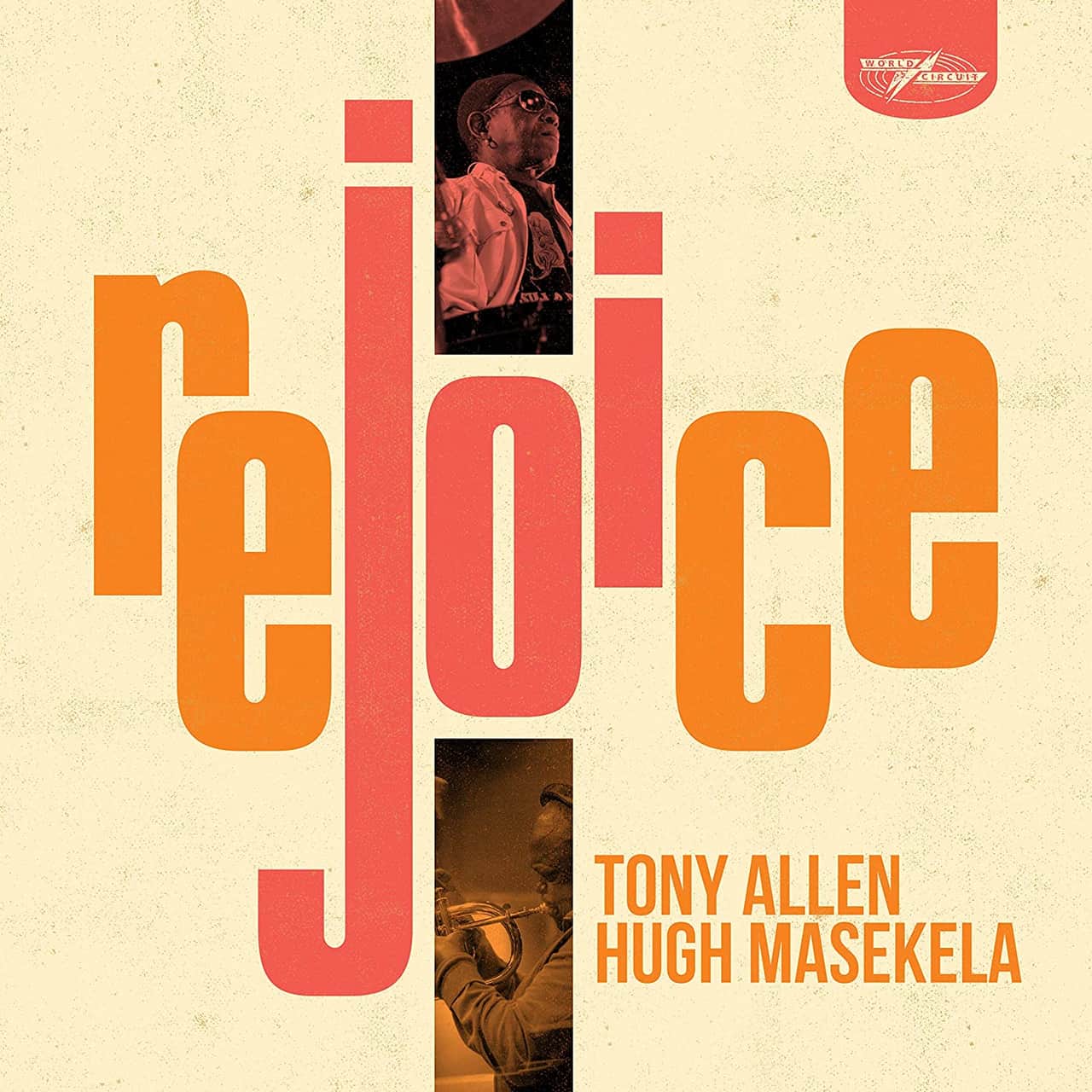
録音自体は2010年なのですが、長らく未発表だったため、リリース的には最も新しい作品になるもの。やはり最近亡くなられた南アフリカのスター、トランペット奏者のヒュー・マセケラとの共同名義の作品。現代UKジャズ・シーンの中心人物、エズラ・コレクティヴのジョー・アーモン・ジョーンズ(key)やココロコのムタレ・チャシ(b)らが参加。暑いアフリカの音楽とは趣の違う、深遠な音、クールなビートに引き込まれます。トニーとヒューの存在が静かに胸に迫ってきますね。



