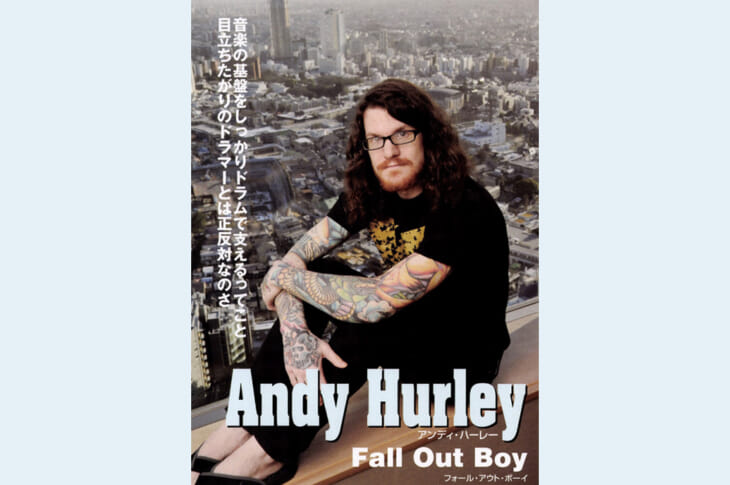PLAYER

UP
ジョン・ボーナム[レッド・ツェッペリン] パーフェクト・バイオグラフィ Vol.01
- Text:Satoshi Kishida
本日9月25日はレッド・ツェッペリンのドラマー、ジョン・ボーナムの命日。1980年にこの世を去って、今年で42年目を迎えた。現在も世界中のミュージシャンに影響を与え続ける、この偉大なるレジェンドを永遠に語り継ぐべく、ここでは2003年6・7月号で掲載した彼のパーフェクト・バイオグラフィを数回に渡って展開していく!
誕生〜鼓動は鳴り止まず〜
ジョン・ボーナム、本名、ジョン・ヘンリー・ボーナムは、1948年5月31日、イングランド中西部の州ウスターシャーの、バーミンガムから10マイルほど南下した町、レディッチに生まれた。彼の祖父ジョン・ヘンリーと父親のジャックは、工務店の看板を掲げる大工で、母親のジョーンも新聞雑誌を販売するスタンド店を切り盛りし、家計を助けていた。祖父から父母、そして子供達ヘと家族に代々受け継がれ守られていたのは、勤勉さと仕事熱心さという気質だったという。ボーナム家の子供達は3人で、長兄のジョンの下に3歳年下の弟マイケルがおり、やがて14歳離れた妹のデボラが生まれた。大きくなってマイケルはラジオDJとして、デボラはシンガーとして有名になり、兄妹みなが後に音楽業界で働くことになる。特にジョンについては、その誕生の時点から非常に興味深い逸話が残っているので、まずは紹介しておきたい。
ジョンの出産は大変な難産だったようで、26時間も陣痛が続いた後にやっと彼が生まれたときには、彼の心臓はすっかり止まっていたのだという。だが担当の看護士が必死に尽力して、まさに奇跡的にジョンは蘇生し、一命を取り留めることができたのだった。一度停止してその後、再び鼓動を始めた心臓を持ったドラマーが、後にレッド・ツェッペリンの、まさに中核としての強靭な心臓部を担うことになろうとは、人生の不思議を感じないわけにいかない。それに、もしこの看護士の努力がなかったら、我々はまったく別の形態のツェッペリンを聴いていたのかもしれず、ロックの歴史も多少なりと変わっていたかも知れないわけだ。
幼少時のジョンとマイケルはたいへんなヤンチャで、いつも殴り合いのケンカをして遊んでいた。だがジョンにはケンカの他にも惹きつけられているものがあった。それがドラムで、5歳の頃から彼は、入浴剤の容器やコーヒー豆の入ったカンにワイヤーを張り、ナイフやフォークでそれを叩きながらスネア・ドラムのような音を出して、家族をイライラさせていた(結局“叩く”ということではケンカと同じわけだが)。最初に根負けしたのが母親で、彼が10歳のときにスネア・ドラムを買い与え、やがて父親が15歳のときにドラム・セットを買ってくれた。中学の頃、14歳のときには、彼は学校内にあったアヴェンジャーズというバンドですでにプレイし始め、卒業時には、自分はプロのドラマーになりたいと周囲にはっきり伝えていたのだという。
彼がドラムに惹きつけられた理由には、最初に父親の影響があった。ジョンの父親はジャズ・ファンで、ベニー・グッドマンの映画をテレビや映画館で一緒に見たり、ハリー・ジェイムズ(tp)のビッグ・バンドのコンサートにジョンを一緒に連れて出かけたりした。そこで彼はジーン・クルーパやソニー・ペインの派手なスティック捌きに魅了されたのだった。ドラムを始めてしばらくは、ジョンは自己流でそうしたドラマーの真似をしていたが、やがて同じレディッチに住む自動車工で、ビッグ・バンドでプレイしているギャリー・オルコックというドラマーの噂を聞き、彼の家に押しかけ一緒に練習するようになる。ギャリーはケニー・クラークの大ファンで、ケニーの豪快なダブル・ストロークの叩き方やビッグ・バンド・ジャズの奏法をジョンに教えた。
次にジョンが知り合ったドラマーが、レディッチで当時最も有名だったビル・ハーヴィだった。やがてビルとジョンは公私を共にするようになり、ビルのバンドでビルの代わりにドラムを叩いたり、一緒にドラム・ソロを共演したりする仲となった。ビルはデイヴ・ブルーベック・カルテットのスウィング・ドラマー、ジョー・モレロの大ファンで、結果的にジョンに、ジョーばりのフィンガー・テクニックや素手でドラムを叩く技を伝授した。当時のジョンは、ギャリーやビルほどテクニックはなかったが、新しい技を知るとすぐに習得し、自分の個性である豪快なサウンドで打ち鴫らした。クラブに他のバンドを見に行って必ず言うジョンの口癖は「あのドラマーはクソだ」だったという。そしてそのバンド・リーダーに自分を売り込み、時にドラマーの座をモノにしてもいた。ジョンはまだ15歳だった。(Vol.02に続く)
※この原稿はリズム&ドラム・マガジン2003年6月号に掲載された記事を転載したものです。