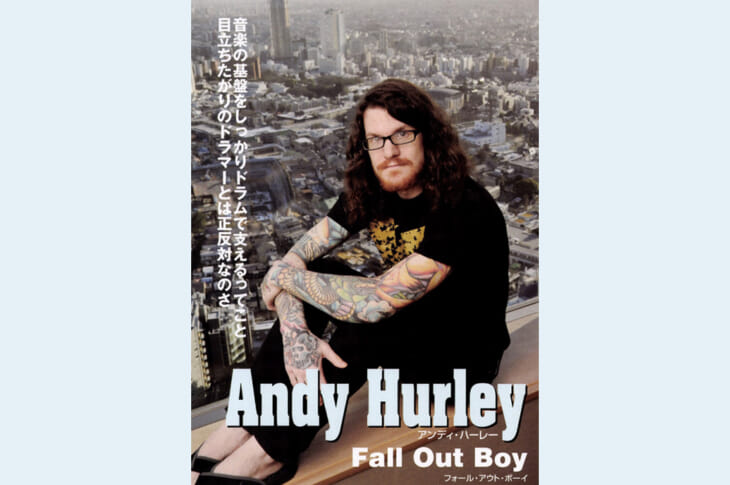PLAYER

UP
【Interview】松田晋二[THE BACK HORN]
- Interview:Rhythm & Drums Magazine Photo:Azusa Takada
自分にはないアプローチや
フレーズの新鮮さを楽しみながらアレンジしていった
●M1「ユートピア」は、これまでのバンドらしさの中にも新たな側面を感じる楽曲で、大きなビート感で打たれるスネアの硬質なサウンドや、ダンサブルなシャッフル感が心地良く、ライヴで演奏されて盛り上がる情景まで浮かぶようでした。アレンジはどのように作り込んでいったのですか?
松田 基本のビートを作曲者の菅波(栄純/g)が打ち込んできて、それをもとにリハーサル・スタジオで叩きながらアレンジしていきました。4つ打ちのキックやキメのユニゾンなどはそのまま生かし、踊れる16分の要素もありながら、ヘヴィなリフにシンプルで太いビートが混ざり合う楽曲にしようと話していたので、イントロやサビのアタマでの16分ハイハットのアクセントを細かくアレンジしたり、間奏部分の6連系のフィルやブレイクも、タムを絡めてブレーキ感を出し、スリリングなフィルになるようなフレーズにしました。
ブレイクのタイミングやそこに向かうフィルの絡め方などは、この曲に限らず作曲者のセンスがさまざまで、自分にはなかったアプローチやフレーズの新鮮さを楽しみながらアレンジしていきました。
●M2「ヒガンバナ」は、静と動の場面が交互にやってくるような“らしさ”溢れるギター・ロックですね。リスナーの背中を後押しするような歌詞と、松田さんのストレートかつ疾走感溢れるビートがリンクしているような印象を受けました。
松田 楽曲が先に完成していたので、そのオケを何度も聴きながら、歌詞が乗る前のこの曲が持つ温度やメッセージを感じ取るところから始めていきました。ドラムのアプローチは楽曲をより強く押し出す激しさや、疾走感を損なわないように意識しました。その中でも特にキックの数に関しては、シンプルで強い8ビートで推すところと細かくいくところのバランスを、メロディとの兼ね合いも見ながら、気持ちのいいところを探して決めていきました。
楽曲のパワーとムードに寄り添い、言葉と曲が必然性を持つような歌詞にしていきたいと思っていたので、結果的にドラムのアプローチも歌詞もつながっていると思います。
●続くM3「深海魚」はレトロ感漂うムーディな曲調ですが、鍵盤なども入った厚みのあるバンド・サウンドの中、ドラムのビートを彩るように、ロー・ピッチでパーカッシヴな音色が重なって聴こえてきます。間奏では、シーケンスと絡む繊細なシンバル・ワークや、豪快な4つ打ちでクラッシュをかき鳴らすようなアプローチも印象的でした。
松田 もとのデモから、大まかなリズム・パターンと、場面の展開、打ち込みのパーカッションやクラップが入ることは決まっていたので、それを受け継ぎながらドラムをアレンジしていきました。曲の冒頭は、もともとデモでは生ドラムは入っていなかったのですが、ハイハットとタム&フロアで、怪しさとサルサのリズムの南国感が出るようにアプローチしました。
間奏部分も、デモではベースと打ち込みのパーカッションだけになるセクションでしたが、アレンジしていく中で16分のノリを感じながらもライドのカップでアクセントをつけたり、ハイハットとパーカッションがユニゾンしたりと、シンバル・ワークだけでも生感を感じられるようにアプローチできたので、打ち込みとシンバルが絶妙な絡みになり、個人的にも気に入っているセクションです。
●なるほど。金モノを効果的に使う上で、どんな工夫をされていますか?
松田 シンバル類の使い方は、アレンジの段階ですごく気にしています。ワイルドに、ビート感をあまり出さずにつながるような激しさを出したいときにはクラッシュでガツガツ刻んだり、ビート感も出しつつソリッドな激しさを出したいときにはハイハット・オープンでいったり、激しさも出しつつメロウな雰囲気を出したいときにはライドをガシガシ叩いたり、ワイルドさもありながら、歯切れ良くビートを出したいときはチャイナを使うなど、何となく自分の中で決めていて、場面の演出によって使い分けるようにしています。
「深海魚」の間奏と「ウロボロス」のサビ、「疾風怒濤」の激しいイントロ・セクションでは、通常のクラッシュ・シンバルではなく、穴があいているパイステ PST-Xの18″のクラッシュを使いました。チャイナよりもサステインが短めで、ピッチも低いので聴こえやすい帯域にあるので荒々しいアタックが出るので、使いどころによっては、リズムを刻むにもこのシンバルは効果的かなと思います。
●ホーンを交えたM4「戯言」は、ジャジーなアプローチと、攻撃的なギター・ロックが絶妙にかけ合わさった場面展開が新鮮です。イントロのピックアップ・フィルをはじめとしてドラムの魅せどころとなるセクションも多く、多彩なビートを使い分けている楽曲ですが、ストーリー展開はどのように考えていったのですか?
松田 「戯言」は、リズム・アプローチが場面ごとに変わったり、テンポも変化するようなスリリングな曲にしたいということで、大まかなアプローチは山田(将司/vo)のデモの段階で打ち込んでありました。初期のデモではピックアップ・フィルはなく、スティックのカウントが入っていたのですが、“瞬発力のあるフィルで曲に入れたら、テンポ・チェンジのスリリングさとインパクトが出るだろう”と思い、キックでフラムを入れた、スネアの8分連打のフィルにアレンジしました。
そのあとのイントロのゴーストのフレーズも、デモではライドのみのアプローチで、ハットのような打ち込みの音色も入っていたので、打ち込みも見えるようにしつつ、ライドとスネアのゴーストや、リムを引っかけたアタックのあるスネアを混ぜたフレージングにして、イントロとAメロのセクションの差別化をしました。
そこからAメロでは、スネアの左手がハイハットに移動しているイメージで、ノリはキープしつつ音色で変化をつけました。間奏のハーフタイムは、4分でとにかく狂気じみるくらいシンバルをかき鳴らしてます(笑)。このセクションの折り返しのフィルは気に入っていて、16分のスネアで引っかけて、シングル・ペダルでキック5発を踏んでブレイクするという渋いアプローチになっているところが個人的に好きです。
間奏からテンポ・チェンジするDメロの流れは、山田とどれくらいゆっくりになってテンポが変わっていくか、かつどんなフィルで次のセクションに向かうかを、何度か話しながら決めました。ドラマーが自然にフィルでテンポを落として次のセクションにいくのを提示するようなアプローチにしたかったので、絶妙なテンポ・チェンジになっていると思います。
この曲の展開とドラム・アプローチが決まってからは、レコーディングまでにひたすらセクションやキメのフレーズごとに練習して、最後につなげて叩く練習をしていました。こういう曲こそ身体に染みついてからでないと良いテイクが録れなそうな予感があったので、レコーディング前の準備としては一番時間をかけた曲だと思います。
Next➡︎「“生ドラムだけでいきたい”というこだわりは、そんなにありません」