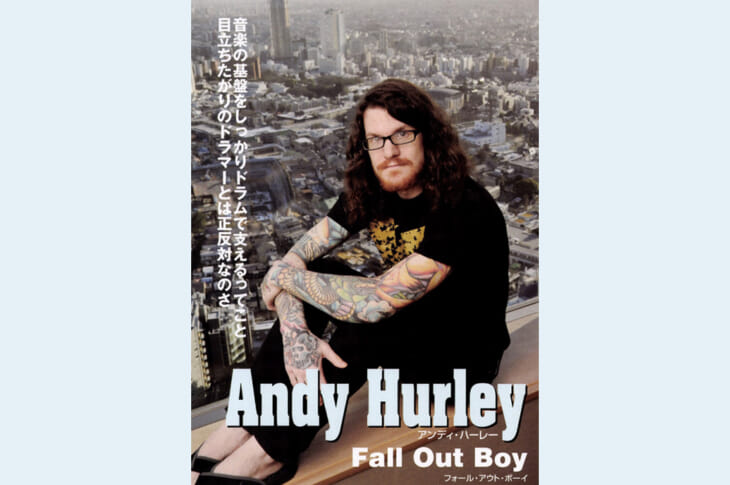PLAYER

UP
【Interview】松田晋二[THE BACK HORN]
- Interview:Rhythm & Drums Magazine Photo:Azusa Takada
アルバムでの曲の立ち位置やムード
ライヴでの演奏をイメージしながら歌詞を考えた

岡峰光舟(b)、菅波栄純(g)、山田将司(vo)、松田晋二(d)
●今作のレコーディングや、バンド内での楽曲作りはどのように進めていったのですか?
松田 楽曲制作自体は、コロナ禍に入る前から変わらず、作曲するメンバーがLogicにデモを打ち込んでチャットに上げて意見交換をして、全体の展開が決まったらドラムをアレンジして、Logicをアレンジした生ドラムに差し替え、そこにベース、ギターとアレンジを進めて各々が録音を重ねて、デモをブラッシュ・アップさせながら楽曲を完成させていくという方法をとっています。
レコーディングに関しては、ドラムと歌だけをレコーディング・スタジオで、ベース、ギターは各々の自宅で録るやり方で進めていきました。今までは1曲ずつオケを仕上げていくやり方でしたが、今回はスタジオに入れる時間も限られていたので、できた曲から1日2曲くらいを目安にして、事前に録る楽曲を集中的に練習してレコーディングに挑みました。
他のパートと一緒に録音することはなかったのですが、完成図をそれぞれが思い描きながら進められたので、楽曲全体を見ながら自分のパートをしっかりと録ることに集中できたと思います。またドラムは楽曲の骨格でもありサウンドの方向性にも深く関わってくるので、長年一緒にやってくれているエンジニアの高須さんとサウンド面についても共有しながらドラム録りを進めていくことで、スネア選びやチューニングなどもこだわっていけたのは良かったなと思います。
●具体的に、今作ではどんな機材を使用したのですか?
松田 基本のドラム・セットは、ずっとライヴやレコーディングで愛用しているDW Collector’s Mapleです。スネア以外の音色は基本、タイトかつしっかりと太みのあるサウンドを目指し、キットのそれぞれの音が立つようにチューニングとミュートで調整していきました。
「ネバーエンディングストーリー」だけは、もう1台所有しているDW Collector’s Mapleの、シェルの巻き方が違うものを使いましたね。カントリー調の曲調に合うように、キックのサイズが22″×16″と浅めのサイズで、ヘッドをコーテッドに替えて温かみを出しつつ、少し乾いた音を目指して録りました。スネアは、ライヴのメインで使用しているDWのSteelを初め、DWのBell Brass、Black Nickel Over Brass、Stainless SteelやAluminumも使用しました。サイズは、すべて14″×5.5″です。
ライヴでは、レコーディングで叩いた歪みスネアや、加工したリム・ショットの音色をRolandのSPDに音源として入れ込み、パッドを叩いてアプローチする方法も考えています。あと、最近はハイハットの音符の長さにも意識がいくようになって。今まで使っていたパイステのダーククリスプというシリーズから、606 フォーミュラの、落ち着いた音色のハイハットに変更しようと思っていたり、ライヴではフロア・タム側にクローズド・ハイハットを設置して、ハイハット・ワークの幅も広げていこうと考えていたりもします。
●ライヴでの表現も試行錯誤されているのですね。今作で松田さんは、「ヒガンバナ」、「深海魚」、「桜色の涙」、「JOY」の作詞を担当されています。作詞とドラムのフレージングは、どちらを先に進めていったのですか?
松田 基本はドラムのアレンジから先に取りかかりましたが、歌詞を想像するために、最初にデモを聴いたときの新鮮な印象も大事にしたかったので、ほぼ同時に考え始めた感じかなと思います。頭の中では常に同時に進行してる感じで、スタジオに入るときはドラム・アレンジを、それ以外の時間は歌詞を考える、というようになるべく時間を使い分けて取り組んでいました。
歌詞のイメージは、それぞれの作曲者にこんな感じはどうだろうか、というのを口頭で伝えたり、「ヒガンバナ」や「深海魚」の場合は、タイトルを決めてから“こんなイメージの歌詞はどうかな?”というのを、チャット上で伝えながら作詞を進めていきました。今回の4曲の歌詞のテーマや内容に関しては任せてくれている感じもあったので、コロナ禍で感じた想いや、自分がトライしたいテーマを探しつつ、アルバムの中での曲の立ち位置や楽曲のムード、ライヴでの演奏をイメージしながら歌詞を考えていきました。
最後に書いた「JOY」に関しては楽曲自体も最後にできて、アルバムのラストを締め括る重要な曲だったので、楽曲ができる前から山田とイメージを共有し、この曲の役割や世界観を言葉で伝え合いながら制作していったので、出来上がったときには“これでアルバムが完成した!”という喜びがありましたね。
Next➡︎「シンバル類の使い方は、すごく気にしています」