SPECIAL
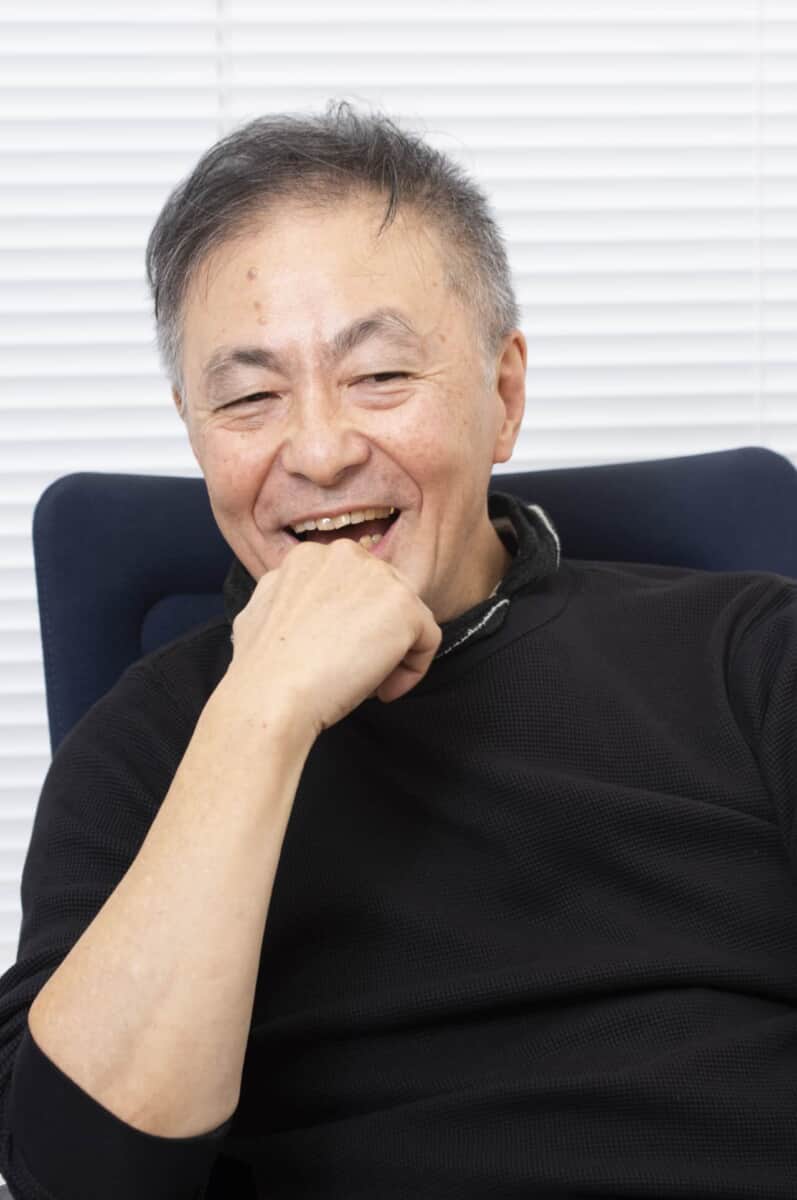

〝そっちの方がカッコいい〞というセンスが似ている
●せっかくの機会ですので、ぜひドラムの話も伺いたいのですが、林さんも幸宏さんも、岩原でドラムを叩きたがらなかった話のように、その後の活動を見ても、ドラム、ドラマーという視点にまったく固執しないという共通点があると思います。それはドラムを始めた頃からですか?
林 たぶん最初からだと思う。好きになった音楽のスタイルがそもそもそうだったし。
幸宏 だって、ドラマーになりたかったわけじゃないですから。
林 そうだよね。
幸宏 林もそうだろうけど、個人的にドラムスクールに通うっていうダサさ、みたいな感覚はありましたね。YMOが終わった頃に、亡くなったスカパラ(東京スカパラダイスオーケストラ)の青木達之君と対談したとき、彼に「ドラムの練習ってしました?」って聞かれたから、僕は「ドラムの練習するくらいなら恋愛しなさい」って名言を残したくらい。その方がいい音楽が作れる。
林 それもわかるけど、今は、練習しときゃよかったなと思う。
幸宏 僕も!
(爆笑)
幸宏 でも、もう自分のスタイルができちゃったからね。今は若い子でもうまい人がすごく多い。
●でも、彼らは林さんや幸宏さんのドラムを聴いて影響を受けているわけで。
幸宏 〝スタイルを作るアイデンティティを持つ〞っていうことは、やっぱり重要だったんですよ。
林 幸宏と話が合うのは、ドラムって練習して臨む楽器じゃないよね、っていう意識が根底にあるんだよね。
幸宏 もっと〝音楽全体〞を聴くべきだっていうね。例えば歌のバックでドラムを叩くんだったら、その〝歌〞を聴くべき。それでシンプルにリズムをキープするならキープする。だから、林とは好きなドラマーが似てるよね――アル・ジャクソンとかバーナード・パーディとか。いざとなったらめちゃくちゃテクはあるんだけど、歌のバックではそういうことはしないという人。
林 〝その方がカッコいい〞っていうセンスが、幸宏とは似てるんだと思う。
幸宏 それで、なおかつ自分のスタイルを持ってるからね。ドラムのチューニングを含めて。逆に〝テクの人〞には興味がなくなっちゃう。海外でもスティーヴ・ジョーダン〔註5〕みたいに、ドラマーであり優秀なプロデューサーでもある人が、アル・ジャクソンを圧倒的にリスペクトしてるじゃないですか。ボズ・スキャッグスの『メンフィス』ってアルバムを聴いたけど、フィルまで完璧にアル・ジャクソンだった。そういう〝普遍的〞なドラマーっているんですよ。僕たちはそういうドラマーが好きなんだよね。
林 本当にそう思う。
●2018年に、幸宏さんのファースト・アルバム『Saravah!』の再現ライブ(Saravah! 40th Anniversary Live)がありましたが、そこでは78年当時、幸宏さんが叩いたドラムを、現在の林さんが再現するという関係でした。
林 あのライブは本当に良かったと思う。僕も気持ち良かったし。
幸宏 オグちゃん(小倉博和)とかター坊(大貫妙子)とかみんな褒めてくれたから、本当に良かったんだなと思った。ドラムのことだけじゃなくて、ライブ全体をすごく褒めてくれて。林が僕のドラムを全部コピーしたのなんて初めてでしょ?
林 生まれて初めて。
幸宏 譜面に書いてたもんね。
林 あれは書かないとできないよ。
幸宏 僕、ヘンなこと演るからね(笑)。林のドラムも当時から独特だと思ってたけど。
●例えば、林さんのドラムのどういうところが独特だと思いますか?
幸宏 パターンが独特なわけじゃなくて、例えば細野さんの「チャタヌガ・チュー・チュー」〔註6〕のアタマのフィルとか、「ハリケーン・ドロシー」の感じとか、複雑なフレーズではないんだけど、シンプルなことをやっていても林のグルーヴ感は普段から16ビートっぽいんですよ。僕はエイト(8ビート)っぽいので、そこは思いっきり違うと思う。僕はエイトでがむしゃらに前に行くタイプ。例えば、クリックがあったら、その(ジャストの点の中でも)一番前のところにスネアがこないと嫌。それはYMOのときから癖になっちゃってますね。で、細野さんのベースは、僕は(ジャストの点の中で)うしろだと思っていんだけど、この間、教授(坂本龍一)と久しぶりに話したら、細野さんのベースも波形で見ると〝前〞なんだって。だから、僕と細野さんは〝前/前〞なんですよ。『HOSONO HOUSE』なんかを聴くと、あの当時から林のドラムも細野さんとすごく合ってたよね。
●林さんは幸宏さんのドラムにどういう印象をお持ちですか?
林 やっぱりメロディを聴いてそれに反応してドラムを叩く、日本では数少ないタイプの人。聴いたらすぐ幸宏ってわかる。それってすごく重要だからね。
幸宏 そういう意味では、林もすぐにわかりますよね。シンプルに叩いていても。これは林、これはポンタ(村上〝ポンタ〞秀一)だってわかるもんね。当然だけど。逆に「これ、僕だっけ?」っていうこともありますけど(笑)。
林 それは僕もある(笑)。
幸宏 ただフィルインで自分だってわかるんだよね。
林 〝幸宏印〞のフィルインがあるからね。
幸宏 林もあるよ。今は「このフィルインっていったらこの人」ってわかるドラマー、あまりいないよね。「うまいな」って思う人はいっぱいいるけど。
林 〝うまい〞人はいっぱいいる。それはそれですごいと思うよ。
幸宏 ジャストだし、チューニングもいいし。……でもね、みたいなところが僕はあるんだけどね。
林 車のデザインみたいなものだよね。力学的に空気抵抗を追究していった結果、今、みんな同じ形になっちゃった。でも、幸宏も僕も、好きなタイプの車って丸めだったりして、どこかちょっと抜けてるというか、隙があるような車で、そっちの方がいいって感じるんだよね。
幸宏 この間、林とちょうどそんな話をツイッターでしたんだよね。フィアットのうしろに革のスーツケースが付いてる写真を見つけて、林が「こんなのがいいんだよね」って言うから、「不便じゃない?」って言ったら、「不便もまたいいんだよ」って。そう言われてみると、僕も27年前に買ったポルシェ、いろいろ不便なところもあったけど、今だに乗ってるからね。
林 そう、〝便利〞だから選んでるわけでは決してない。
幸宏 もうエンジンの音からして違うから、あれじゃなきゃダメなんだよ。
林 乗るときの〝気分〞だよね。自分の好きな靴を履くのと、ビーサン履くのは違うもんね。
幸宏 そう、その通り。極端な話をすると、僕はドラムを叩くアイデンティティって〝格好〞まで含んでたからね――「この靴でドラム叩いてるのは世界中で僕だけ」とかさ。
林 観客からは見えないのにね(笑)。
幸宏 それはさすがにトノバン(加藤和彦)にも言われた、「幸宏、観客から見えないけどいいの?」って(笑)。しかも「つま先に傷がつくよ」って。
林 僕は、ドラムを叩くときは、だいたいソールが滑らない硬めのスニーカータイプにしてるけど、幸宏とポンタは、どんな靴でもバスドラ踏めるよね。それが信じられない。
幸宏 むしろ、スニーカー履いてたら、ドラム叩くときに革靴に履き替えるタイプだよ。
林 そうか、幸宏はそもそもカカトを床に着けて踏んでるから、滑らないんだ。
●幸宏さんがおっしゃる〝見えない部分まで含めて〞アイデンティティというドラマーは、今少ないかもしれないですね。
幸宏 極端な話、食べるものも飲むものも、全部含めてですよ。
●生活すべてが出るということですね。
林 そこは大切ですよ。
幸宏 別に高級なものを食べるって意味じゃないですよ。
林 そう、その通り。そういえば、2人でご飯食べ行っても呑み行っても、やっぱりドラムの話はいっさい出ないね(笑)。
幸宏 音楽の話はするけど、たしかにドラムの話は出ないね。
林 AFTER SCHOOL HANGOUT〔註7〕(以下、ASH)のときは、タカ(沼澤尚)と3人で、クリームのジンジャー・ベイカーのドラムをもろコピーしたね。
幸宏 「ストレンジ・ブルー」のフィルをもろコピーで、ぴったり合わせてやろうって、〝タダッ・タタドドタタドド〞って。
林 見てる人が喜んでくれたかどうかはわからないけど(笑)。
●60年代当時は、ジンジャー・ベイカーもコピーしていました?
林 ジンジャー・ベイカーは、そんなに好きなタイプじゃなかった。
幸宏 僕もだね。やっぱり2人とも手数が多すぎる人はあまり好きじゃないんだよね。うまい人は好きだけど、〝うまい〞っていうのは手数が少ない中でずっといいグルーヴを提供しているっていう意味でね。だって、ドラムってキープするのが役目じゃないですか。インスト・バンドは別だけど。
林 ジミヘンもクラプトンも当時トリオで3人しかいなかったから、ドラムで埋めなきゃしょうがなかったんだろうね。しかもベースも動きまくるし。
幸宏 しかも、ベースはソウル的な動き方じゃなくて、ピックで弾きまくる感じだもんね。でも、(ハードなロックでも)当時フリーとかはカッコ良かった。ポール・コゾフ(g)とアンディ・フレイザー(b)がね……やっぱりドラムじゃない。サイモン・カークは音がデカいのはいいんだけどね。
●ASHはカバー・バンドですが、ライブはまさにお2人がティーンエイジャーの頃に戻っているようなセットリスト〔註8〕でしたね。
林 思いっきり、十代の頃のど真ん中だね。
幸宏 ASHこそ、そうだね。セットリストの1/4くらいは岩原で演ってた曲(笑)。あれからたいしてうまくなってないという。
●林さんと沼澤尚さんのダブル・ドラムをバックに、幸宏さんがギターを持って歌い、時に3人によるトリプル・ドラムのシーンもありました。
林 たしかに、幸宏が前に出てギターを弾いて歌ってる姿は、岩原の光景に近い。何よりこうして今も、幸宏とそういうライブができる関係だってことがいいよね。
幸宏 ASHでは茂もいるからね。茂もまったく変わってなくて、野外のライブに出たとき、袖でこれからステージに上がろうかっていうときに、「1曲目なんだっけ?」って聞いてきたときにはびっくりした(笑)。
林 (笑)。さぁ行くぞ!っていうときにね。
幸宏 結局は、集まると昔のノリになるんだよね。社会的には大人になってるんだろうけど、たいして変わらないという。
林 いきなりあの当時に戻っちゃうのが楽しくてしょうがない。それを、僕たち3人以外のメンバーがおもしろがって見てるんだよ。世界的に見ても、同じ世代のミュージシャンがこれだけずっと続けていて、また集まってるっていう状況って、他にないんじゃないかな。それはおもしろいなと思う。
幸宏 確かにないね。奇跡というか運命的なものを感じる。よく「あの時代の東京に、どうしてそんな連中がたまたまいっぱいいたんだろう?」って言われるけど、やっぱり当時は、ロックをやるっていうのは、ある程度親にお金がなきゃできなかったんじゃないかな。だからハングリー精神なんてまったくなかったもんね。
林 お腹はいつも空いてたけどね(笑)。
註5 スティーヴ・ジョーダン:1970年代からニューヨークの最先端フュージョン・シーンで活躍するも、80年代中盤、ニール・ヤングやボブ・ディランなど多数アーティストの録音に参加し、ロック畑での目覚ましい活躍を見せる。キース・リチャーズのソロ作を共同プロデュースしたことをきっかけに、作曲から単独プロデュース、映画やコンサートの音楽監督を務めるなど新たな次元でシーンを創造し続けている。
註6 「チャタヌガ・チュー・チュー」/「ハリケーン・ドロシー」:どちらも1975年作『トロピカル・ダンディー』所収。
註7 AFTER SCHOOL HANGOUT:「放課後、みんなでジャムるのが待ちきれないほどワクワクさせてくれた曲がいっぱいある。その〝感じ〞を理解し、表現できる最高の仲間たちが奇跡的に集まった」という2015年結成時の林の言葉通り、林、沼澤尚のダブルドラムを中心に、鈴木茂、森俊之(key)、沖山優司(b)、ボーカリストとして高橋幸宏とLeyonaが集結。
※この対談は『東京バックビート族 林立夫自伝』より転載したものです。また、3月15日発売のリズム&ドラム・マガジン2023年4月号では、1月11日にこの世を去った高橋幸宏さんに哀悼の意を込めて、追悼特集を掲載しております。ご予約はこちら→https://amzn.to/3FxfIxB

東京バックビート族 林立夫自伝
林 立夫(著)
定価:2,200円(税込)
1970年代初頭から、現在に至る日本ポップスの新たな”起点”となり活躍し続けてきた名ドラマー、林立夫の自伝。50’s少年期から60’s学生時代、小坂忠や松任谷正隆らと組んだフォー・ジョー・ハーフを端緒に、キャラメル・ママ、ティン・パン・アレーを経てスタジオ・ミュージシャンとして一時代を築き、80年代”引退”にともなう第二の人生、そして、90年代の復帰から現在の活動まで、あらゆる時代を通して、いかにして音楽的な創造力やセンスを培い、どんな想いで各時代を駆け抜けてきたかを、本人の語りによって明らかにする。青山育ちである著者がさまざまな人間関係を築いた”昭和・東京”、そこには、50’~60’sのR&Rやポップス=”バックビート・ミュージック”に多大な影響を受けた”ギャング”たちがいた。彼らがその後、日本のポップス界に残してきた功績はあまりにも大きい。荒井由実、大滝詠一、大貫妙子、鈴木茂、高橋幸宏、細野晴臣、矢野顕子など、第一線のアーティストと共に、日本ポップスにグルーヴを刻み込んだ最重要人物である林立夫、その存在と生き方に今こそフォーカスするべきである。
●詳細はこちら→https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3119317109/
●オーディオ・ブック版はこちら→https://audiobook.jp/product/266320




