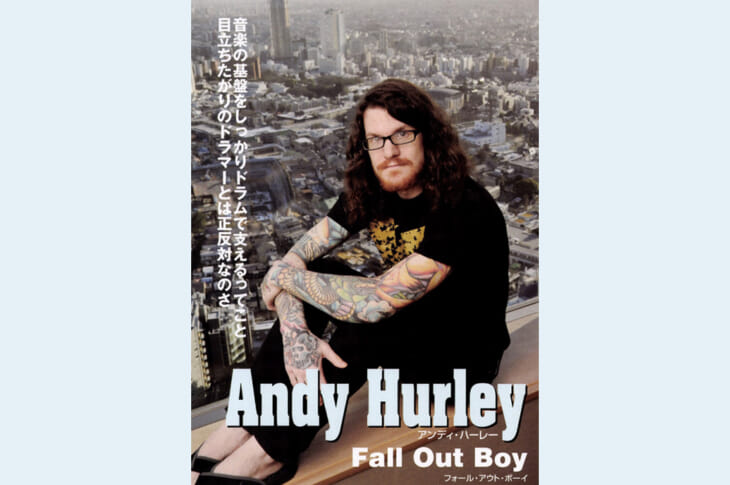PLAYER

UP
Interview – 小泉 拓[クリープハイプ]
いろいろなことに柔軟でありたい
メンバーがどう考えているのかを知り
じゃあこれはどうだろうと
提案できる自分でありたい
クリープハイプが約3年3ヵ月ぶりとなるアルバム『夜にしがみついて、朝で溶かして』をリリース。コロナ禍だからこその手法や納得いくまで繰り返した試行錯誤の軌跡が感じられる今作は、1曲1曲から新たなサウンドや曲調のアプローチが感じられ、バンドの新境地を思わせる。今回のドラム・アプローチはどのように構築していったのか、小泉 拓が語る。

ユニバーサル UMCK1705
楽曲が良くなるのであれば
極端な話
ドラムが出てこなくてもいい
●コロナの影響で制作や発売にも影響があったとは思いますが、『泣きたくなるほど嬉しい日々に』から約3年3ヶ月ぶりとなるアルバムですね。
小泉 今回のアルバム制作期間中は、バンド内で“打ち込みの音の強さ”だったりがキーワードとしてありました。サブスクなど、昨今の音楽の聴かれ方を考えたときに、せっかくこだわって作ったバンド・サウンドが、打ち込みの音楽と比べて音が弱く聴こえる、ということが懸念材料としてあり、そこをいかにして改善するか、というのが1つ課題になっていました。そこでバンドの音像をあらためて見直し、ギターを弾かない、ドラムを叩かない、というようなことにも挑戦しました。
●実際の制作はどのように進められましたか?
小泉 コロナ禍だったということもあり、スタジオに入らずに、リモートでデータのやり取りをしながら曲を詰めていく、という手法も制作方法の選択肢に加わりましたね。自分としては、そのことが新鮮だったし、受け止めることもできました。リモートでの良さは、全員で楽曲を客観的に聴きながら進めることができる、という点が挙げられるかと思います。スタジオでの制作は、良くも悪くも、ドラム・セットで演奏したものが基準になってしまい、そこからなかなか脱却するのが難しい、ということもあったので。
●バンドとして変化のあった時期でもあったわけですね。
小泉 制作においては、自由であることが大事だと自分は思っていて、楽曲が良くなるのであれば、極端な話、ドラムが出てこなくてもいいと思っています。制作した楽曲を、ライヴで実際にどう演奏するかは後で考えるとして、まずは本当に良いと思える形で楽曲を完成させる。そういう方向に、よりシフトできたのは収穫かなと、個人的には思います。ドラマーとしては、そういうことが許容できるようになった、ということが挙げられるかもしれません。打ち込みと生演奏、どちらにも良さがあって、その使い分けというか、自分の中での棲み分けというか、そういったものも見えてきました。
●これまでのクリープハイプらしいロックがありつつ、サウンド的にもドラムのアプローチ的にも非常に音が整理されていて、今までとはまた違った“聴きやすさ”を感じました。「料理」はその代表例なのかなとも思いました。
小泉 歌詞が出来上がってくるのが制作の一番最後だったりするので、歌が入った状態の楽曲を聴いて初めて辻褄が合う、というような感覚を持つことがあります。「料理」についても、歌詞がない状態で曲をアレンジしていき、その段階でリムやカウベルといった音を、尾崎の方からリクエストされて、自分は音だけでその曲の雰囲気だったりを解釈して演奏します。歌が入って、「料理」という曲名がついた状態で聴くと、リムやカウベルの音が、まな板で包丁を使う音や、鍋蓋と鍋がぶつかる音だったりに聴こえてきて、自分でも面白いと思います。どこまでが尾崎の中での想定内なのかはわかりませんが、偶然にしろ、そういったことが起きるのが、バンドで曲を作る面白みでもあるな、と思います。
●「ポリコ」や「モノマネ」も、系統的には同じ路線、ということになるのでしょうか?
小泉 「ポリコ」は、サウンドに関しては、ガレージっぽい感じというようなリクエストがあったので、自分の中でのそれっぽい感じを意識した演奏をしながら、アレンジをしましたね。この曲も、歌が入る前と後とで、自分の中での印象が変わった曲です。特にサビはキメっぽいのフィルが3回あるのですが、歌メロと絶妙に絡んでいて、個人的にはとても気に入っています。
「モノマネ」に関しては、この曲を制作していた時期ぐらいから“打ち込みの音の強さ”をより意識し始めたように思います。この曲は普通に生ドラムで演奏していますが、音像については、楽曲に馴染む音というよりかは、リズムが点で見えるような、前に浮き出てくる音にしたい、といった話をエンジニアさんに相談したりもしました。