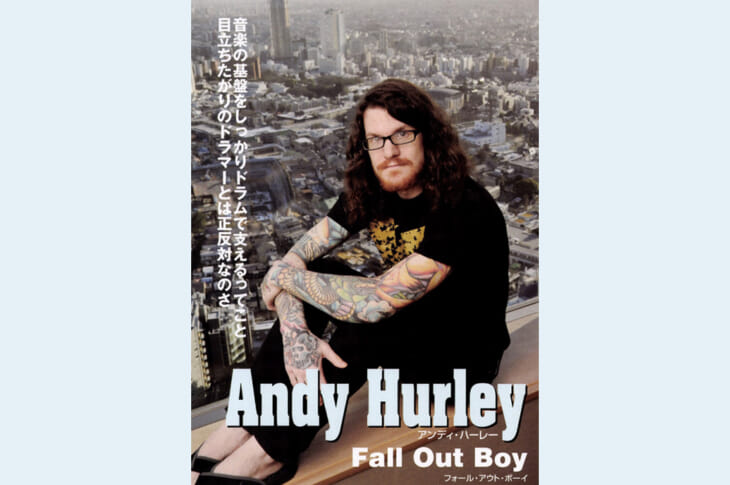PLAYER

UP
【Report】ディープ・パープルが5年ぶりに来日! イアン・ペイスが円熟のドラミングで日本武道館のオーディエンスを魅了!!
- Photo:Masanori Doi/Akito Takagawa(Gear)
- Special Thanks:UDO ARTISTS Inc.
1968年に結成され、今年で55周年を迎えるディープ・パープル。ロック界の生ける伝説が2018年以来、約5年ぶりに来日! 唯一のオリジナル・メンバーであるイアン・ペイスを核とした熟練のパフォーマンスで日本のファンを魅了してくれた。そんな来日公演のレポートをお届けしよう!

2018年の来日は“The Long Goodbye Tour”と題したワールド・ツアーの一環で、そのタイトルからバンドの終焉を予感させたが、結成から半世紀を過ぎても彼らの創作意欲は衰えることを知らず、コロナ禍においてオリジナル・アルバム『WHOOSH!』とカヴァー・アルバム『TURNING TO CRIME』の2作品を発表。2022年からは延期になっていたツアーも本格的に再開していた。
“UNLEASHED IN JAPAN”と銘打った今回の来日公演は、東京、広島、福岡、大阪の4都市を巡るショート・ツアーで、編集部が訪れたのは初日=3月13日の日本武道館。名盤として誉の高い『ライヴ・イン・ジャパン』の収録会場の1つで、その後も幾度なくライヴを行ってきたバンドとファン、双方にとって聖地とも言える場所。イアン・ペイスにとってもまたしかりで、特殊な構造の武道館に響き渡るドラム・サウンドを久しぶりに体感し、懐かしさを感じていたのではないだろうか。

定刻過ぎ、客電が落ち、壮大なSEが流れる中、メンバーがステージに登場。拍手が巻き起こる中、ペイスによるスネアの8分打ちが鳴り響き、「HIGHWAY STAR」からライヴはスタート。長年の相棒=ロジャー・グローヴァーのベースとガッチリとロックし、推進力のあるグルーヴを刻み出す。バンドのカラーを決定づけるドン・エイリーの鍵盤も冴え渡り、イアン・ギランも熱いシャウトで冒頭から会場を沸かせていく。





最大のトピックは、昨夏にバンドを脱退したスティーヴ・モーズに代わる新ギタリスト=サイモン・マクブライドの存在で、43歳とメンバーよりも二回り若い彼の存在がバンドに新たな息吹を与えていたように思う。そんなエネルギッシュなバンド・サウンドのエンジン役を担うペイスは、力みのないフォームからスウィンギーなビートを繰り出し、曲のラストではテクニカルなショート・ソロも披露するなど、今年75歳になるとは思えないほど切れ味抜群だ!

序盤から中盤にかけては、「PICTURES OF HOME」、「NO NEED TO SHOUT」、「NOTHING AT ALL UNCOMMON MAN」、「LAZY」、「WHEN A BLIND MAN」と、72年発表の代表作『Machine Head』と目下の最新作『WHOOSH!』を織り交ぜたセットリストが展開されていく。
印象的だったのは、メンバーの誰1人としてイヤモニをしていなかった点。ホール・クラスの会場において、イヤモニは今や当たり前となっているが、PAシステムが発達していない時代から、数多くのステージを経験してきた百戦錬磨の彼らには必要ない模様(代わりにペイスはドラム・セットの背後の耳の高さの位置にスピーカーを2台設置)。シーケンスや打ち込みなどの同期もなく、スピーカーから流れてくるのは5人が奏でるアンサンブルのみ。音数が少ないからこそ、1人1人が鳴らす音が強固で、ニュアンスもしっかりと聴こえてくる。
また、イヤモニなしということで、当然ながらクリックもなし。『WHOOSH!』のリリース・タイミングで行ったインタビューでは、「最初にクリックを使わなきゃならなかったときにはとても嫌で、演奏が制約されるような感じがしたし、クリックは敵だとさえ思った」と話し、「ステージではもちろん、クリックは使わないよ。でもスタジオでは使っている。ただ、クリックを使うとどうしても雰囲気が出ないと思ったときには、クリックを使わずにコントロールを保ちながら全員で演奏することはあるけれどね」と語っていたペイス。
この日も曲のムードや会場の盛り上がりに合わせて突っ込む/タメるなど自由自在。「NO NEED TO SHOUT」はスクリーンに映し出される歌詞とシンクしていたが、そういった場面ではマシンの如くカッチリとタイトにキープ。クリックが普及する以前から、長年に渡って第一線で叩き続けてきたレジェンドの貫禄が随所に感じられる。

ペイスが使用する機材は、26″のバス・ドラムを基調としたパールのマスターワークスに、パイステ2002シリーズを組み合わせた左利き用のセッティング。点数は多いが、演奏する際の基本は13″TT、16″FT、18″FTで、1バス、1タム、2フロア・タムという往年と同じ王道のロック仕様。シンバルもかなり高くセットされているが、椅子も高いため、無駄のない最小限の動きでプレイ。そこから奏でられる音色は、キャリアを重ねて、ますます多彩さを増しているかのよう。


全体的に高めにセッティング。右端のチャイナを除いて水平に並んでいる点にも注目。


前述のインタビューでは「昔ほどの音量は出していないけれど、今はそれほど大きな音を出したいとは思わない。音量を抑えて、腕や肘よりも指でスティックをコントロールすれば、より多彩なドラミングができることがわかっているからね」とプレイ・スタイルの変化についても語っていたが、フィンガー・コントロールは実に繊細で、シャッフルにおけるゴースト・ノートの使い方も見事。ダイナミクス表現はもちろん、音の抜き差しやフレーズの歌い方、そして“ここぞ!”という場面でのスピーディなスティッキングも含めて、70年代の黄金期とはまた違う円熟のドラミングでオーディエンスを魅了していたように思う。

キーボード・ソロを挟んでライヴは終盤へと向かい、ハイライトは「SPACE TRUCKIN’」に続いて演奏された「SMOKE ON THE WATER」だろう。誰もが知るイントロのギター・リフに、ペイスによるハイハットの16分刻みが絡み、さらにメンバーの音が重なって、歌へと雪崩れ込むアレンジはオリジナルとほぼ同じで、わかっているのに痺れてしまうカッコ良さ。ギターとキーボードそれぞれのソロやオーディエンスとのコール&レスポンスなど、ライヴならではの要素も加わって、会場も熱気を帯びていき、ラストはペイスによるツイン・ペダル連打で締め括った。
アンコールでは豪快なロールからスタートする「HUSH」が披露され、曲終わりでペイスとロジャーによるリズム体ソロへと突入。舞台上を練り歩きながらベースを奏でるロジャーも、それに呼応したビートを刻むペイスも、とにかく楽しそうな表情が印象的。そしてソロの流れからカウントが入り、代表曲「BLACK NIGHT」を熱演! 約100分間に渡るステージは大団円を迎えた。

サイモンという若く才能豊かなギタリストが加入し、半世紀を超えるキャリアを経て、また違ったフェーズへと突入した感のあるディープ・パープル。本番が始まる前までは、これが最後の来日公演になるのではないかと勝手に想像していたが、近い将来、再び日本にやってくるに違いないと予感させる力強いパフォーマンスであった!