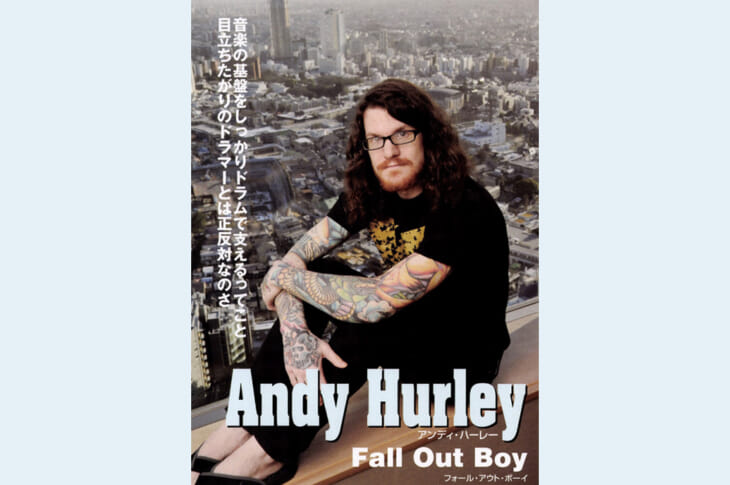PLAYER

UP
『カンバセーション・イン・ジャズ ラルフ・J・グリーソン対話集』発売記念! MJQを支えた名手、コニー・ケイがルーツを語る!!
20世紀アメリカの著名なジャズ・ジャーナリスト、ラルフ・J・グリーソンによるインタビュー集『カンバセーション・イン・ジャズ ラルフ・J・グリーソン対話集』(訳:小田中裕次)が1月25日に発売! その中から、長きに渡ってモダン・ジャズ・カルテット(MJQ)を支えた名ドラマー=コニー・ケイのインタビューの一部を抜粋して転載!
●ドラムスを演奏するようになったのはいつ頃ですか。
CK 実は、よく分からないんです。子供のときだったのは確かです。ハーレムにあった「コットンクラブ」―古い「コットンクラブ」ですね[一九二三年から三六年まではハーレムで、ハーレム暴動の後、三六年から四〇年まではミッドタウンで営業した]。そこからキャブ・キャロウェイがラジオ放送されていて、夜になって、私がキャブ・キャロウェイかデューク・エリントンを聞くまで母が寝かせてくれなかったんですよ。
居間に母の足乗せクッションがあって、私はいくつかハンガーの棒を取りはずしてドラムスティックを作りました。ナイフを使って何本かドラムスティックを作るわけです。夜はいつも起きていて、キャブ・キャロウェイの演奏に合わせて[クッションを]叩くんです。キャロウェイが出演するのは夜の十一時半頃だったと思います。遅い時間ですが、仮にベッドに入っていても、キャブ・キャロウェイが登場するまで眠ろうとしませんでした。それからキャロウェイが退場すると、そこでやっと眠るわけです。とにかくそうやって過ごすのが好きでしたね。
母はピアノ教師で、ピアノを教えていましたけど、私はいつもドラムスを叩きたがっていました。放課後にアルバイトができるような年齢になった頃、母がウーリッツァー[Wurlitzer:ドイツ発生のピアノ・メーカー。アメリカで電気ピアノ、ジュークボックス、エレピ等を製造]へ出かけて、分割払いでドラムセットを一組買ってくれたので、放課後のアルバイトで貯めたお金でドラムスの代金を支払いました。だから実際のドラムスを演奏し始めたのはそのとき以来ということですね。
近所に知り合いがいて、彼の叔父さんがドラマーか何かでした。私が確か一〇歳とか一一歳くらいのときで、その叔父さんがスネアドラムを置いていったので、こっそりとそのスネアドラムを持ち出して、アパートメントまで持ち帰ったことがよくありましたが、ドラムセットを演奏したことは、そのときまで一度もなかったんです。
●それはタッカホー[マンハッタンの北方二五キロにある、ニューヨーク州タッカホー村]でのことですか。
CK いや、それはニューヨークです。私はタッカホー生まれですが、夏以外そこで暮らしたことはないんです。叔母と叔父がタッカホーに家を持っていたので、毎夏そこへ行って夏を過ごしていましたが、事実上はニューヨーク育ちなんです。
私はそういう音楽が好きでしたが、当時ラジオで、唯一聞けたのがキャブ・キャロウェイだったんです。彼がよくやっていたのが〈ハイデハイデホー〉で、そういう曲に何となく引かれていました。でもドラムスの部分だけ取り出して、ドラムスを聴いたことは一度もないです。私はただ、キャロウェイと一緒に演奏できるから、その音楽を聞きたかったわけで、それだけでした。
●その後、プロとして演奏を始めたのはいつ頃ですか。
CK それには面白い話があるので、お聞かせしましょう。プロとして演奏を始めたのは、初めてのドラムセットを私が手に入れた四日ほど後だったんです。
●準備完了だったわけですね。
CK 私がドラムスを手に入れたのは、確か月曜日か火曜日で、私の家は通りに面した一階にありました。私はずっと叩いていましたが、家のすぐ近所にナイトクラブがあって、そこのバンドで演奏していた三、四人とは知り合いでした。
そのバンドで演奏していたドラマーがいて、彼が仕事場に現れなかったので、誰かが「近所にドラムスを叩いているヤツがいるよ」と言うと、また誰かがこう言いました。「ちょっとそこへ行って、そいつが練習しているのを聞いてみたらどう。近所にドラマーがいるんだぜ。そこへ行ってみて、雇えばいいさ」。というわけで、みんなで家にやって来て、ドアをノックして、「今晩働く気はある?」と訊くので、私が「ええ」と答えると、「あのね、仕事があるんだ。誰それが現れないんだ。じゃ、一緒に来いよ」って言うんです。それで、そのクラブへ行ったわけです。その男のドラムスがもう何もかも置いてあったので、自分のドラムスを持っていく必要もありませんでした。
というわけで、すぐにその仕事にありついたんです。実際はジャズの演奏ではなくて、ショーだったので、私にとっては良い経験になりました。いたのはコーラス・ガールとコメディアン、それにタップダンサーなんかですね。ですが、おかしなことに、ハイハットを二拍、四拍で鳴らせないんです。緊張しすぎてハイハットをコントロールできなかったんですね。みんなで演奏を始めるたびに、私が二拍、三拍でハイハットを鳴らすので、結局ハイハットの演奏をあきらめましたが、いずれにしろあの当時は、それほどハイハットは使われていなかったんです。みんな大方はライドシンバルを使っていて、左手でバックビートを叩いていましたが、私はそれができたので仕事を続けられました。というのは「あんたはタイムキープがいい。それがいちばん大事だからな」って言われましたから。「この後もずっと頼むよ」と言ってくれたんです。まだ高校に通っていたときでしたからね。確か、一六歳とか一七歳くらいのときだったと思います。
●それは何年頃でしたか。
CK 一九四〇年かそのへんですね、戦争が始まったのが四〇年だから、四二年だったと思います。でもその後「ミントンズ」に行くようになって、「ミントンズ」でディジー、バード、バド・パウエル、モンク、レイ・ブラウン、ドン・バイアス、デューク……とかとジャムっていました。
●お母さんがドラムスを一式買ってくれたときに、自分はミュージシャンになろうと思いましたか。
CK というか、ミュージシャンになりたかったんです。理由の一つは、弁当箱を抱えて昼間起きているのが楽しくなくて、それが嫌いでした。昼間起きて学校へ行くなんてなおさらでしたが、そうしなきゃなりませんからね。ですから、それがミュージシャンになりたかった理由の一つで、たぶん私は、まさに夜型人間だったんでしょう。
●ドラムスの勉強はしましたか。
CK あまりしてませんね。演奏というものを始めたのが、ピアノを少々弾けるようになることだったので―振り返ると、ピアノが好きじゃなかった理由はそれでしたね。ピアノを初見で弾くのが苦手だったんです。
音は全部分かっていました。ピアノの[鍵盤の]どこが何の音かは分かっていたんです。でも、いつも楽譜を見なければならず、それからピアノに目を落として、自分が正しい音を弾いているかどうか確かめなきゃならないわけです。でも、一度曲を覚えてしまえば、譜面を閉じても演奏できました。譜面を初見で弾くのが苦手で、それがピアノの演奏に興味を失った理由の一つでした。おまけに私が間違った音を弾くと、母がいつも私の指をぴしっと叩くんです。鉛筆とかそういうもので叩くので、それがイヤでした。
母は毎年リサイタルを開いていました。「あのね、お母さん、僕はドラムスを演奏したいんだ。ピアノは弾きたくないよ」と私が言うと、母は「じゃあ、今年のリサイタルで弾きなさい。そうすればドラムスのセットを買ってあげるから」って言うわけです。「ピアノ教師の息子がピアノを弾けなかったら、みっともないでしょう」とも言いました。そうやって母は私にいっぱい食わせていたんです。
毎年私は頑張りましたが、ドラムスは買ってもらえないんですよ。それで自分で買えるような年齢になって、やっと手に入れたわけです。というのは、母は音楽好きでしたが、実はミュージシャンの人生が最高だなんて思っていなかったんです。大抵の親がそうだろうと思いますが、私には医者とか、弁護士とかになって欲しかったんですね。
●兄弟とか姉妹はいますか。
CK いいえ、私は一人っ子です。それで母は、ずっと医者か弁護士になって欲しいと思っていたんです。でもおかしなことに、その最初の仕事には母が行かせてくれたんですよ。父はと言えば、この件にはむしろ懐疑的で、「分かったわ、行ってらっしゃい」と言ってくれたのが母だったんです。私には二人の許可が必要でしたから、「こういう人がやって来て、そこで演奏して欲しいと言ってるんだ。やってもいいかな」と訊きました。そうしたら母は、「そうね、お父さんの意見を聞いてみたら」って言うんです。
二人を比べたら、父の方が新しいもの好きで、世間のことを知っていたので、それもあって私を行かせたくなかったんでしょう。父は「あまり賛成できないな」って言ったんです。すると母が、「行かせて、やらせてあげましょうよ」と言ってくれました。でも結局のところ、両親は私のことをすごく助けてくれました。というのは、多くの連中が仕事で苦労していましたし、両親も仕事を見つけたらどうだと時おり私に言ったことはありましたが、食べることと、眠ることに関しては、私は一度も心配したことはなかったからです。ある意味で、これは良いことでしたね。というのはギグがなければ仕事もないということですから。
仕事の間隔がずいぶん長かったことが何度かありましたが、二人とも仕事をしろと口うるさく言うことは決してありませんでした。ほんの時おり母が、「クリスマス繁忙期なんだから郵便局でも行って、仕事を見つけたらどうなの。二人とも、あなたに食べさせるのに疲れたわ」と言ってましたけど。
●あなたは幸運でしたね。
CK おっしゃる通りです。私のように気楽に暮らせた人間はほとんどいませんから。それに関しては両親に感謝しています。
●でも、ドラムスをやるのに、ピアノという楽器が役に立ちましたよね。
CK ピアノで私が理解できるのは、音価[音の長さ]です―つまり、ドラムスというのは音価が分かってさえいればいいんです。音階上のラインはあまり意味がありません。重要なのは音の長さで、私にはそれが分かっています。そのおかげで私はドラムスの譜面は非常によく読めましたし、それに自分が正しく叩いているかどうかを振り返って調べる必要もありませんでした。
ピアノの場合、自分が正しい音で弾いていたかどうか確かめる必要がありますが、ドラムスの場合は単にリズムを聞いていればいいわけです。そこでドラム教本を買いましたが、えーと、最初に買ったドラム教本はジーン・クルーパ[シカゴ出身の白人ドラマー]のもので、当時彼は大物でしたからね。いや、このクルーパのドラム教本はすごくて、スティックの持ち方、プレスロールのやり方、一拍とは何か、一拍中の四分音符とは、二分音符を一回叩いて二つ数えるには……とか、そういうようなことが書いてあったので、大部分自分で独習しました。
それからニューヨークにドラムショップがあって、ビル・メイターズ・ドラムショップというところへ行きました。私はよくその店まで出かけて行きましたが、そこにドリュー・スコットという人がいました。その人はスコットランド人で―スコットランドかアイルランド人のどちらかだったと思います。彼は、あの独創的なドラム奏法、何と言ったかな、そう、バグパイプ楽団でドラムを叩いていたんです。
●軍人でしょうかね。
CK その人が良い教師だという話を、何人かのドラマーが言っているのを聞いていました。そこで何度かレッスンを受けたんです。でも、私はその当時はもうかなりの間、仕事で演奏していましたけどね。
●当時現役のドラマーで、誰か名の通った人から教えてもらいましたか。
CK シッド・カトレットですね。この人については面白い話があります。一緒に腰を下ろして、スティックを持ったり、ドラムパッドやドラム教本を使ったりしたことは実は一度もなかったんですが、座ってただ彼と話をして、それもドラムスの話ではなくて一般的なことばかりで、それなのに彼からもっと大事なことを学びました。
あの人の話しぶりや、人生の出来事で何を感じたかとか、それによって、彼がなぜああいうドラムスを演奏するのか、私には理解できたんです。仮に正面切って、「シッド、これはどうやって、あれはどうやっているのか、あれとこれを教えてください……」とか言うよりも、その方がドラムスについてもっと学べたと思います。彼とずっと一緒にいましたし、まるで友だちみたいでした。私は本当にそこから多くのことを学びました。
●彼は素晴らしい人でしたね。
CK とてもビューティフルな人でした。シッドが亡くなったとき[一九五一年]は本当に悲しかったです。実をいうと、私は大好きなミュージシャンを二人亡くしましたが、両方ともそのとき私は近くにいませんでした。それがレスター・ヤングとシッド・カトレットです。
レスターが亡くなったとき[一九五九年]、私はこちら[西海岸]にいました。ニューヨークに、何となくうんざりしていたんです。仕事があまりうまく行かなかったので、フランク・タリーとのロックンロールの仕事をこちらで見つけて、南部へ行って六週間から二ヶ月くらいの間、いくつか一晩興行を続けていましたが、その間にプレズ[レスター・ヤング]が亡くなったんです。ちょうど戻って来る途中で訃報を聞いたと思います。あるレストランにいて、ニュース映画でそれを聞きました。
●不思議なことに、あなたがシッドに関して語ったのと同じことを、今は非常に多くのドラマーが言っています。シッドのあとに現れたあらゆるドラマーにとって、彼は明らかに父親のような存在だったということですね。あらゆることに驚くほどの影響を与えています。
CK 私はとても幸運だったんだと思います。というのは、私ほど、彼が親しくしていたドラマーは他にいませんでしたから。まったくの幸運でしたが、私はボロボロの五三年型のスチュードベーカー[車の名前。シッド・カトレットが亡くなったのは一九五一年なので、これは四三年型の誤りか?]を持っていて、ある晩五二丁目へ出かけたんです。
そこへは当時しょっちゅう行っていましたが、実際にシッドと知り合いだったわけじゃありません。クラブはもう閉店するようになっていた時代でしたが、実は私はまだ仮免しかなくて、車の運転は許可されていなかったんです。運転するには大人の同乗者が必要でした。同じ建物に住んでいた男がいて、その人は大昔にアルトサックスを吹いていて、バンドか何かを持っていましたが、もう吹くのはやめていました。当時は実はトラックの運転手をしていて、ぶらつくのが好きだったので、車でどこかへ行きたくなると、その人の部屋に行って、「ねえ、五二丁目とかそのあたりまで行ってみない」と言うと、「そうだな、いいよ、そうしよう」と言ってくれました。私が合法的に車を乗り回すにはそれしか方法がなかったんです。
そういうわけで、その晩はもう準備ができていたし、[シッドが出演していた]店も閉めようとする時間だったので、たぶんシッドが車に乗りたがっているかもしれないと思ったんです。そこで、彼に「シッド、アップタウンに帰るんですか? それなら、車で送りますよ」って声をかけました。するとシッドは―彼の好きな言葉は〝若いの〟(buck)だったので―「ああ、若いの、アップタウンに行くよ。それじゃ乗せてもらおうか」って言ったんです。
その当時シッドは一三八丁目に住んでいて、そこは通りをはさんで「ルネッサンス・カジノ」の真向かいでした。そこへ向かう途中で私たちは話を始めて、私は少しドラムスをやっていることを彼に伝えました―ちょうど今の若者が私に話すみたいな感じでね。「あそこに見える建物があるだろう? 私はあそこに住んでいるんだ。いつでも来なさい」と言ってくれました。
そんなわけで、以来ずっと、シッドは私を手放せなくなったんです。彼はよく私に電話してきたりして、親しい友人のようになりました。電話してきて「実は、どこそこへ行かなきゃならないんだけど、そこまで乗せて行ってもらえないかな」って言うんです。それで私が車で迎えに行って、ギグの場所までよく送って行きました。
あるとき彼らは短編[映画]を作りましたが、当時はジョン・カービー[ヴァージニア州出身のベース奏者]と共演して短編をよく制作していたんです。それで、その現場までシッドを送って行きましたし、あるときなんか私のドラムスを貸しましたが、それは「ビリー・ローズのダイアモンド・ホースシュー」[ニューヨーク出身の興行主ビリー・ローズが、パラマウント・ホテル地下に開いたナイトクラブ]へ行ったときのことです。ショーでドラムスをどう配置するか確認するのにドラムスが必要で、彼のドラムスはどこか別のところに置いてあったんです。「ちょっと、ドラムスを貸してくれよ。何がどうなっているのか分かるように、ステージにドラムスをセッティングしなきゃならないんだ」と言ってね。
彼のドラムスを私の家であずかっていたことさえあります。シッド・カトレットのドラムスが自分の家に置いてあるなんて、とんでもないことだぜって思いましたよ。彼のドラムスは何度かあずかっていたこともあります。そんなふうにして、二人は相棒みたいになった、というわけです。
訳者注:Conrad Henry Kirnon ; Connie Kay (1927 – 94)
ニューヨーク州タッカホー村生まれのドラマー。独学でドラムスを習得し、一九四〇年代半ばからロサンゼルスで演奏活動を開始。一九四九年からレスター・ヤングのクインテットに在籍しながら、スタン・ゲッツやコールマン・ホーキンズ等とも共演していた。その間、R&B のセッションにも参加し、ビッグ・ジョー・ターナーのヒット作『Shake, Rattle and Roll』(1954 Atlantic)のレコーディング等にも参加した。一九五五年に退団したケニー・クラークの後任としてMJQに加わり、その後MJQ最後の録音となった結成四〇周年記念レコード『MJQ&Friends』(1993 Atlantic)まで、数多くのレコードに参加した。その間MJQ以外にも、ジョン・ルイスやミルト・ジャクソン名義の名盤をはじめとする数多くのジャズ・レコードに参加している。本インタビュー時の年齢は三二歳。
MJQ以外の代表的レコーディングの一枚に、ジョン・ルイス(p)、パーシー・ヒース(b)、コニー・ケイ(ds)のトリオにバリー・ガルブレイス(g)とジム・ホール(g)を加えた名盤『The John Lewis Piano』 (1958 Atlantic)があり、ここではケイの真骨頂というべき繊細なドラミングが聞ける。本インタビュー直近のレコードは、インタビュー中で触れているチェット・ベイカー(tp)のバラード中心のアルバム『Chet』(1959 Riverside)で、ドラムスは全十曲のうちコニー・ケイが六曲、(たぶん途中で行方をくらました?)フィリー・ジョー・ジョーンズが四曲、他にハービー・マン(fl)、 ペッパー・アダムス(bs)、 ビル・エヴァンス(p)、 ポール・チェンバース(b)等が参加している。
*本記事は『カンバセーション・イン・ジャズ ラルフ・J・グリーソン対話集』の一部を抜粋したものになります。
『カンバセーション・イン・ジャズ ラルフ・J・グリーソン対話集』
価格(本体価格):¥2,500(税込:¥2,750)
四六判 448ページ
2023.01.25発売 ISBN:9784845638338